
みんなはどうやって決めてる?
夏休みも終盤に差し掛かり,まもなく受験中盤に突入します.
塾の夏季講習や学校の補修なども終わり,ここからの勉強戦略を立てる人も多いことでしょう!!
ここで問題なのが…
今からどうやって勉強すればいいんだ?
ということでしょうか…
5月,6月あたりの模試の成績が返却され自分の現在の位置が分かってきた人もいるでしょうが,そこからさらに飛躍するためにはどんな参考書や問題集を使って勉強をすればいいのか
そんな話をしていこうと思います!!
Step1:志望校を決めよ!!
これを聞いて「ハァ?」と思えた人は問題ないです
受験生の中には
「とりあえず勉強はしているけど明確に志望校は決まってない」
という層が一定数存在します.
別に悪いことでは無いんですよ.
ただ,それで受験を軽々とクリアできるのは灘や開成に通う地頭がフィーバーしてる秀才レベルくらいなもんです
一般受験生は明確に目標・志望校を持って、その大学に合わせて勉強することです。
- 勉強スケジュールをカスタム
- 勉強方法の工夫
ですので現時点で志望校が明確では無い人はこの記事を見た「一週間以内に」志望校を決めてください!
一旦…例を作ってみます

僕は名古屋大学の理学部に行くんゾー!!
今回はこの象さんを例にして色々と決めていきましょうか!
Step2:試験内容と配点をチェックしよう!
では次にStep2ですが,志望校が決まったら?
その学部学科の
・入試科目
・配点 をチェックしよう!
🔎[名古屋大学 理学部 入試科目]
なんかで調べれば出てくるでしょう.

名古屋大学の理学部の入試科目を調べるゾー!!


なるほど!
・共通テストの圧縮はなし
・2次試験の比率が高め
・現代文が出題される
名大の特徴がわかったゾー!
大学によっては共通テストの得点が圧縮されたり,2次試験の配点比率が低かったりします.
- 共通テストが圧縮される場合→個別試験の対策を充実する必要がある
- 2次試験の比率が少ない場合→共通テストの対策を充実する必要がある
今回は2次試験の方が比率が高いので,そちらの対策を優先しようと思います.
Step3:過去問を見て頻出分野をチェックしよう!!
次に大事になってくるのは過去問の出題傾向です.
闇雲に数学の問題を解いていくのも1つの手ですが,如何せん受験まで残り期間が少ないわけです…
そうなるとより効果的な対策をする必要があるので,一旦過去に出されている問題から傾向を掴みに行きましょう!
<名古屋大学の過去問の傾向ー過去5年分>
| 年度 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |
| 2023 | 複素数平面 | 微積 | 微分 | 論証 |
| 2022 | 整式と微分 | 確率 | 複素数と図形 | 積分・論証 |
| 2021 | 微積 | 対数・整式 | 確率 | 漸化式 |
| 2020 | 2次曲線 | 整数 | 積分・論証 | 確率 |
| 2019 | 積分計算 | ベクトル | 整数 | 確率 |

確率の出題頻度が高いゾ!
他にも微積は毎年頻出で,整数も狙われやすそうだゾ!
逆に,ベクトルや数列をメインテーマにした問題は比較的少ないってことも分かってきたゾ!
※大門の中で様々な知識を必要とする問題は出てきますが,今回はメインテーマにフォーカスしました.
・過去の出題傾向を知ると,対策の優先事項が決まってくる
・赤本や青本などで過去問を見ておくと,そのレベル感までわかるので尚良し!
⇩
すると闇雲に問題を解く必要が無くなってくる!
Step4:現時点での自分の実力と相談しよう!!!
最後に…ようやく参考書選びに入るわけですが,ここで重要なのは今の自分の状態を知っておくことです.

直近の模試の数学の偏差値は58〜63くらい…
その中でも
微分積分と整数は得意だけど…
確率が苦手なんだよな〜

確率は基本的な知識や計算ができるんだけど,何かと複合した問題を出されると考え方に悩んじゃうんだよな〜
さて,こんな場合はどんな問題集を使えば良いでしょうか?
ここからは個人的な考えですが,「網羅系の参考書」や「総合演習的な問題集」はまずオススメしません.
確率の複合問題が苦手なので例えば
河合塾・場合の数と確率
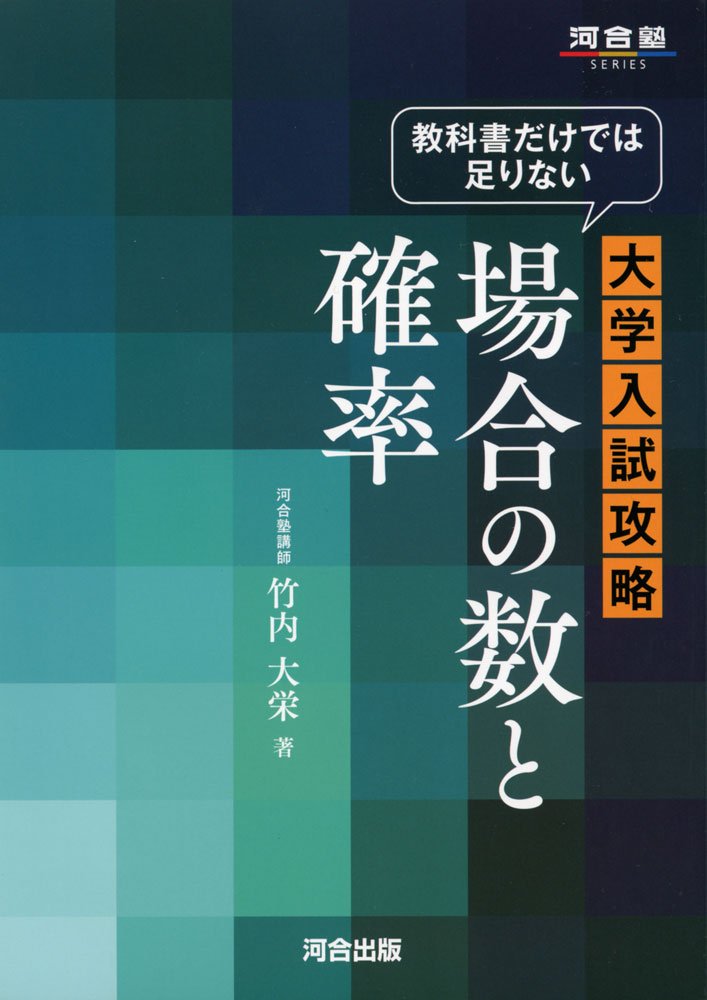
東京出版・ハッと目覚める確率
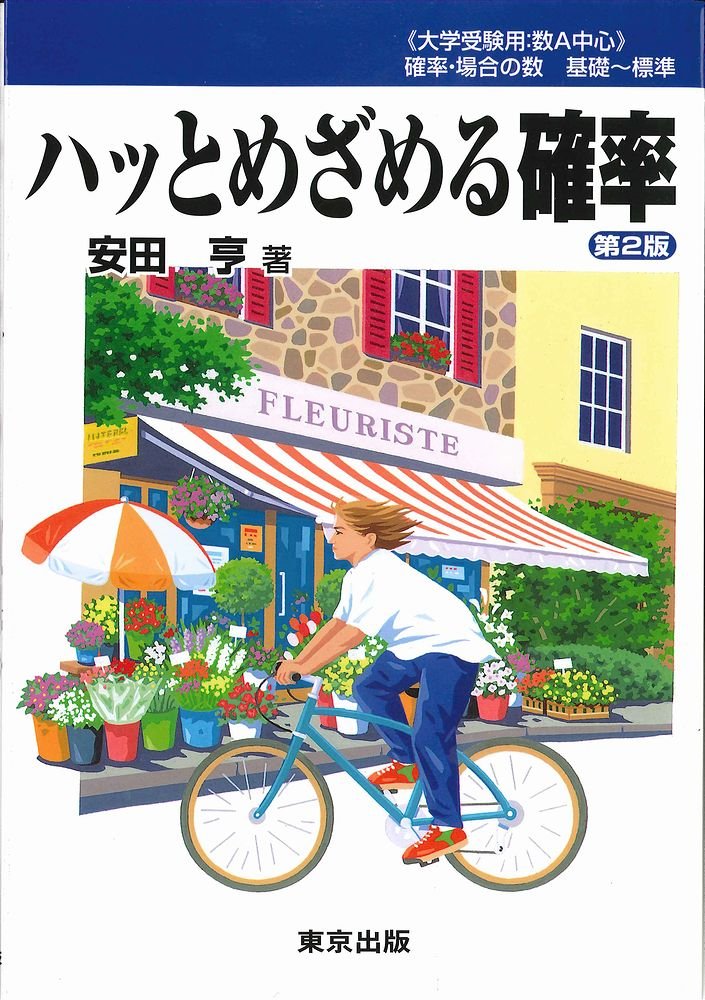
などをオススメします.
確率を完全マスターするなら・・・
解法の探求・確率―大学への数学(激ムズ)
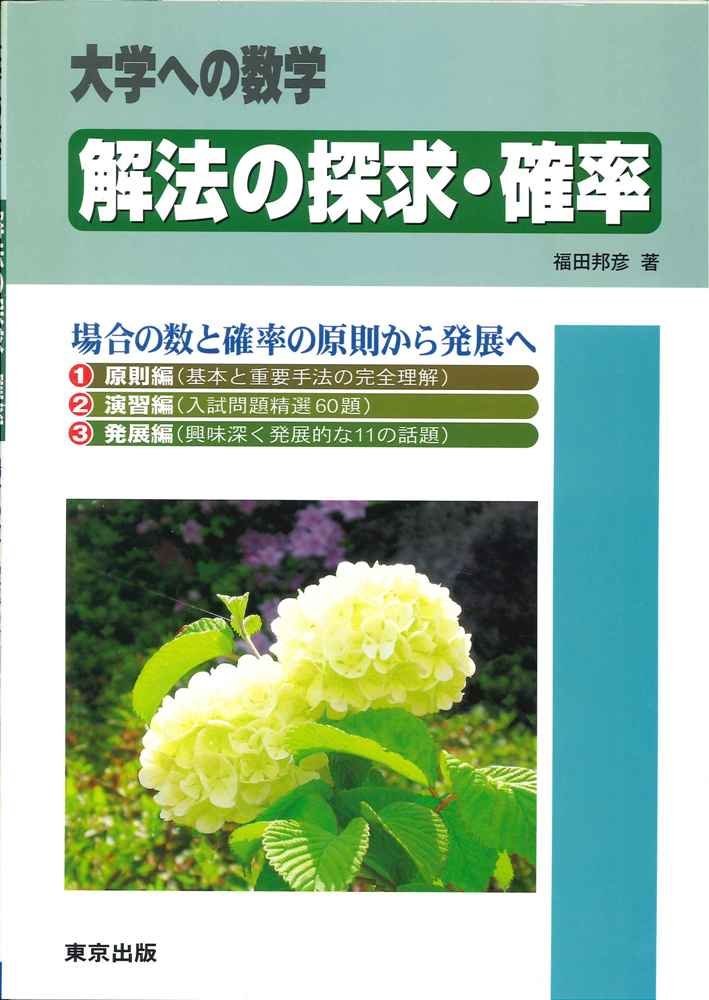
なんかもあります^^
そこで十分に確率の対策ができたら直前期(11月~)に入った段階で
理系数学・入試の核心 難関大編
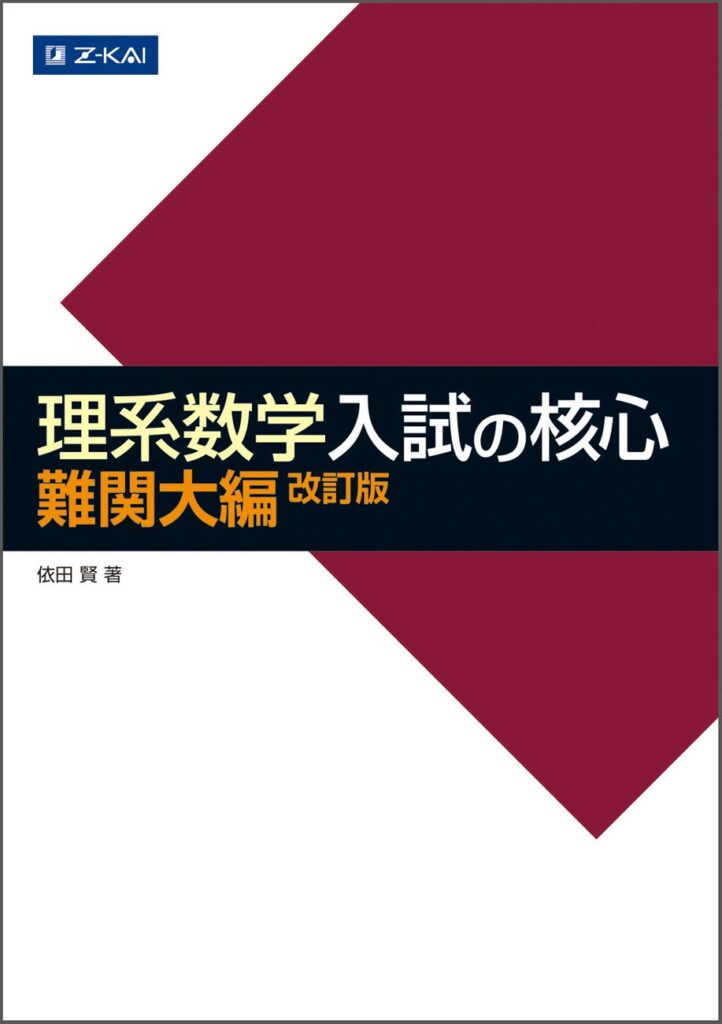
名古屋大学・理系数学15ヵ年
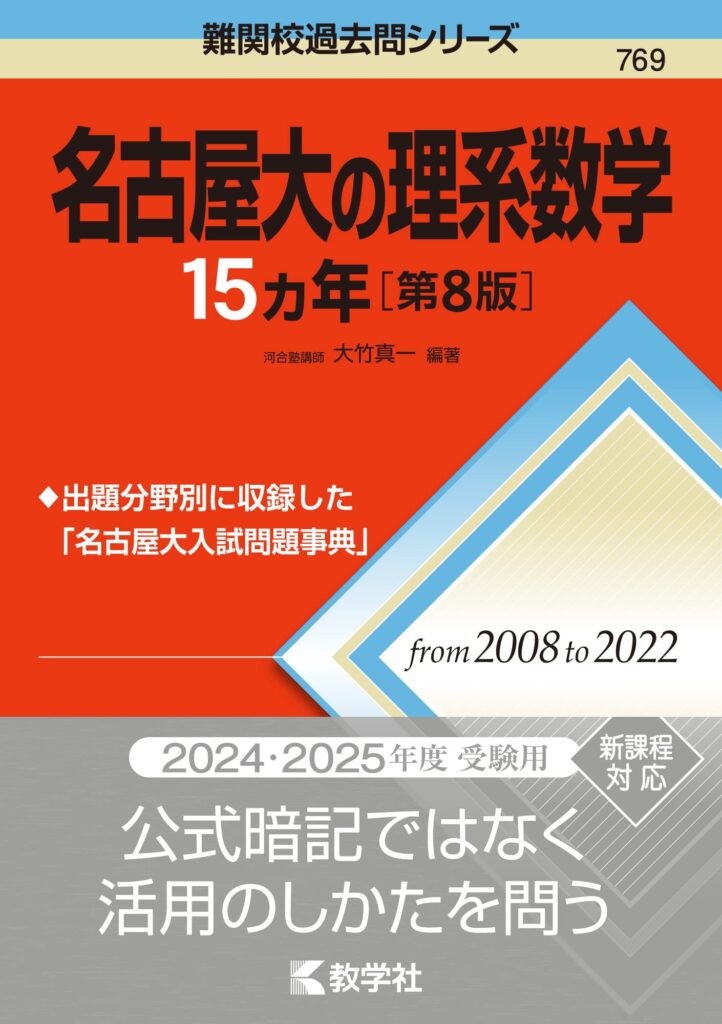
などをオススメします.
受験中盤戦(9月・10月)はまだピンポイントな対策が有効です.
今のうちに苦手を完全に潰しておいて後半戦に備えられる,そんな参考書・問題集選びをしてみるのも一つの手だと思います.
まとめ
- 志望校を決めよう!
- 入試の科目や配点をチェックしよう!
- 過去問の傾向を分析しよう!
- 今の自分のレベルと大学の傾向を総合的に判断して適切な1冊を決めよう!
ここから先は具体性を持った対策に挑んでくださいね!!
また,スタサプなどの外部機関を利用して対策することも有効だと思うので検討してみてください!






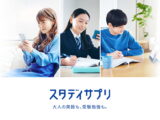


コメント